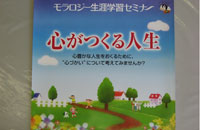ブログカテゴリ
月別一覧
商品サービス一覧
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
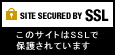
|
ホーム |
ブログ
ブログ
記事検索
ブログ:3328件
蔵書印 3 「あ! そうか!」
蔵書印 2
蔵書印
竹久夢二展
心がつくる人生
稲刈り 4
稲刈り 3
稲刈り 2
稲刈り 1
ティーポット ?
父の道具 4
海 3
海 2
海
鹽竈神社 例大祭
柴栗
スズメバチ ③
父の道具 3
父の道具 2
黄金色の稲穂
|
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス